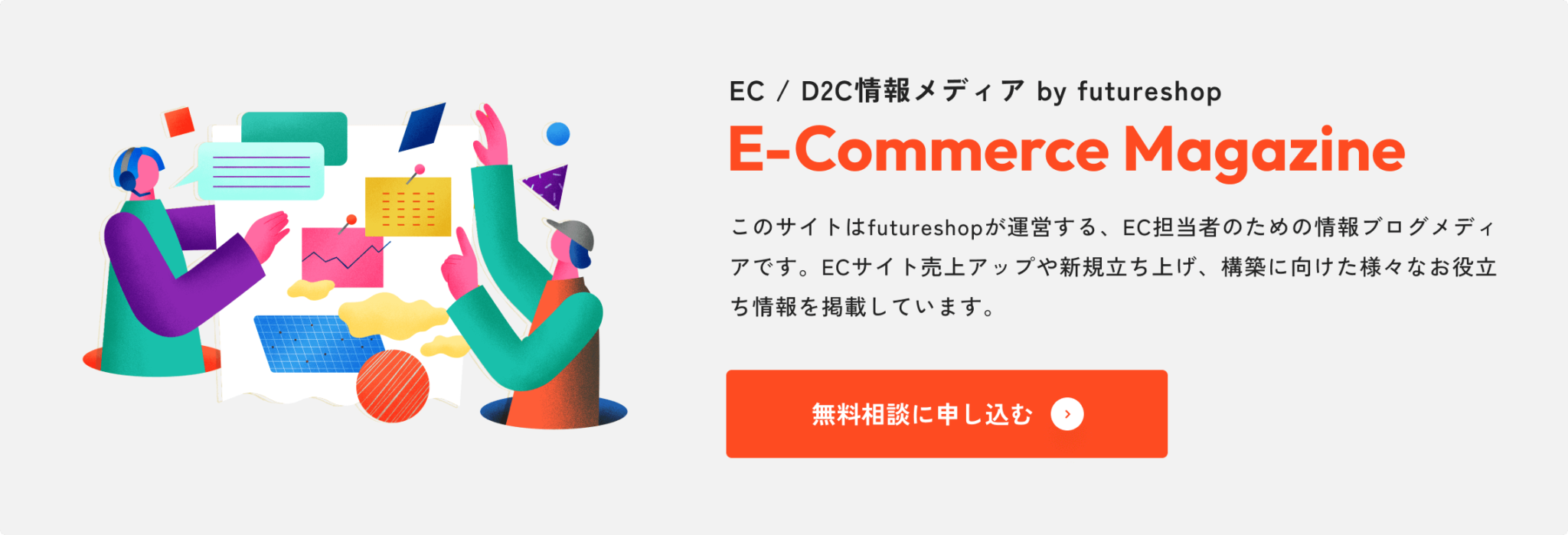EC事業を手がける際は、さまざまな関連法規を遵守する必要があります。EC事業者さまに影響する法律の動向について、一般社団法人ECネットワーク理事の沢田登志子さまに寄稿していただきました。第2回は、ECサイトの利用規約などに関わる民法(債権法)と消費者契約法の解説です。
民法(債権法)と消費者契約法について解説
こんにちは。ECネットワークです。今回は、民法(債権法)改正で導入された定型約款と、消費者契約法についてご紹介します。利用規約に書いておけば何でも有効というわけではない、という話です。
Ⅰ.定型約款とは何か
1. 120年ぶりの債権法改正
民法の中で、契約に関する基本的な規律を定めた部分を債権法と言います。親族法や相続法には戦後大きな改正がありましたが、債権法は、明治29年の制定以来、根本的な改正はなく、カタカナで読みにくいままでした。時代の変化に合わせて内容も見直し、一般国民にわかりやすいものにしようと検討が始まったのが2009年です。法務省法制審議会での8年の議論を経て2017年に改正法が成立し、2020年4月から施行されています。
改正内容は多岐にわたりますが、特に注目したいのが定型約款に関する規律(第548条の2、第548条の3、第548条の4)です。ウェブサービスでは今や当たり前の「利用規約」ですが、これまで民法には該当する規定がありませんでした。契約の一部なのか何なのか、中身を読んでいない相手を拘束できるのか、事業者側で勝手に定め、自由に変更することが許されるのか等について、明文のルールがなかったのです。今回創設された規定で、これらが初めて法律的に整理されました。
運送約款や保険約款は聞いたことがあっても、定型約款という言葉には馴染みがないと思います。平たく言うと「不特定多数の相手方に同じ内容で提示する契約条件」です。Eコマースでは、特定商取引法の表示とは別に、利用規約を定めていることがありますね。会員登録の際に提示する会員規約も定型約款に当たると思います。この場合は、規約を作る側であるショップが定型約款準備者として規律の対象です。相手方は顧客です。B2C取引でなくても定型約款に当てはまるものはありますが、本稿では、ショップと顧客との取引にしぼって説明します。
2. 定形約款の表示・同意取得の必要性
利用規約が定型約款に当たるとしたら、これまでの運用と何か変える必要があるのでしょうか。
新民法では、「定型約款を契約の内容とすることに合意があれば、約款の個別の条項にも合意したとみなす」と定められました(第548条の2第1項第2号)。「規約に同意」ボタンが必須でないばかりか、条文上は、定型約款の内容を事前に表示することも必須ではないとされたのです(請求があったら開示する義務が別途あります)。
これは、リアルでは、定型約款の全文を表示するのが難しい場面もあることが考慮されたものと思います。 とは言え、インターネット取引では規約本文へのリンクを常に見えるところに置き、消費者がいつでも内容を確認できる状態にした上で、必要に応じ同意ボタンを押してもらう、という流れが既にスタンダードになっているので、そのまま踏襲していただくのが最良かと思います。
なお、規約への同意プロセスを入れていない場合には、「定型約款を契約の内容とすることについて合意があった」と言えるように、表示の仕方を少し工夫する必要があるかも知れません。弁護士さんへのご相談をお薦めします。
3. 不当条項に注意
規約の内容をしっかり表示し、同意ボタンが押されていたとしても、個別の条項について合意があったと認められない場合があります。いわゆる不当条項です。第548条の2第2項では、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、信義則(民法第1条第2項に定める信義誠実の原則)に反して相手方の利益を一方的に害する条項は合意がなかったものとみなす」とされています。
例えばEコマースで、「不良品でも返品・交換はしない」「お試し商品を注文したら自動的に定期コースの契約申込みとなる」といった条項がもしあったら、この部分については合意がなかった(=契約条項として有効でない)とされる可能性がありそうです。
定型約款による契約の相手方(Eコマースの規約であれば消費者。以下、相手方と表記)は、通常、その内容を事前に詳細に確認したりはしません。それでも個別の条項に同意があったとみなして良いのは、不当な内容が含まれていないという「信頼の前提」があるからです。顧客に不利な条件については、規約の中に潜り込ませるのではなく、別の形でしっかり説明した上で明示的な同意をもらっておかないと、無効と判断されるリスクがあるということですね。
消費者契約法にも不当条項の規定があり、もう少し具体的に定められています。これについては後述します。
4. 同意なく変更できる場合とその手続き
Eコマースの売買契約は、通常、注文ごとに交わされますが、会員規約は継続的な契約です。ポイント付与をやめるといった場合は、会員規約やポイント規約を変更することになります。契約は両当事者の合意で成り立つという原則からすると、契約内容の変更には相手方の同意が必要です。しかし相手が多数の場合にいちいち同意を得るのは現実的でない、相手によって変更したりしなかったりという運用はあり得ない、という問題について、旧民法には答えがありませんでした。
実務としては、規約の中に「事業者の判断でいつでも内容を変更できる」という規定(いわゆる変更権条項)を置き、ある程度柔軟に変更してきたのではないかと思います。民法第548条の4は、その考え方を若干修正し、相手方に同意を求めない変更について 一定の要件を課すものです。
他方、相手方の同意を取得しなければ変更はできないはず、という原則重視の考え方からすると、第548条の4は、逆に変更の要件を緩和したということになります。
では、どんな場合であれば、同意によらずに定型約款を変更できるとしたのでしょうか。まず、「相手方の一般の利益に適合するとき」です。ポイント付与率をアップしたり有効期限を延ばしたり、という変更に文句を言う消費者はいないでしょうから、このような変更は認められます。
もう1つは、「変更が契約した目的に反せず、かつ、変更に係る事情に照らして合理的であるとき」です。実例を挙げるのは難しいのですが、セキュリティ上の理由で少し使い勝手が悪くなる、といったことでしょうか。 合理的かどうかの判断にはさまざまな事情が考慮されますが、「変更権条項の有無」も考慮要素の1つになると解説されています。その他、変更を望まない相手が契約を解除できる措置を採っているかどうか等も考慮されます。
変更するための手続きも規定されました(第548条の4第2項)。変更の効力がいつから発生するかを決めて、サイトやemail等で事前に周知する必要があります。事前とはどのくらい前か?という疑問が湧くと思いますが、民法は行政規制とは異なり、そこまで細かいことは決めていません。内容によって当事者が適宜判断しますが、例えば周知期間が短かったことが原因で相手方に不利益が生じた等の紛争に発展した場合は、最終的には裁判で解決することになります。今後、裁判例が出てくれば参考にできると思われます。
Ⅱ.消費者契約法の不当条項規制
1. 消費者契約法とは
民法(債権法)がB2CもB2BもC2Cもカバーする取引一般法であるのに対し、消費者契約法は、B2C取引にのみ適用される法律です。2000年に制定され、現在は消費者庁が所管していますが、特定商取引法や景品表示法のように「違反したら行政処分」というタイプの法律ではなく、民法の特別法として、民事裁判で争う際の判断基準です。
Eコマースのように少額の取引では、トラブルになっても裁判まで行くことはめったにないですが、少し法律知識のある消費者や消費生活センター等が消費者契約法を主張の根拠とする場合があるので、現場担当者も知識を持っておく必要があると思います。
消費者契約法には、大きく2つのルールがあります。1つは「不当勧誘による契約は取消可能」、もう1つは「不当な契約条項は無効」というものです。
従来、Eコマースの商品広告は、勧誘とは考えられてきませんでした。しかし2017年の最高裁判決で、紙のチラシが勧誘に当たるとの解釈が示され、Eコマースも不当勧誘ルールの対象とされる可能性が否定できなくなりました。広告表示については既に十分注意をされていると思いますが、行政処分に加えて取消リスクもゼロではないとお考えください。
とはいえ不当勧誘ルールは、高齢者を狙う悪質な訪問販売や、若年層が騙される就職セミナー商法などを主に念頭においたものなので、本稿では、不当条項のルールを紹介します。
2. 消費者の権利を一方的に害する条項は無効
消費者契約法第10条は、「消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する条項」で一定の要件を満たすものは無効と定めています。民法第548条の2第2項と同じような規定ですが、消費者契約法は、定型約款に当たらない個々の契約条件も対象です。また、事業者と消費者は情報量や交渉力に格差があるという前提に立ち、その格差を埋めるために、事業者側に責任が重く課されています。
第10条では、「消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する」例として、「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項」を挙げています。サプリメントAを注文したらサプリメントBが同梱されてきて、消費者が「Bは不要」という意思表示をしない限り、サプリメントBについても注文したとみなす、といった事例を指していると思われます。もっとも、これだけで直ちに不当条項となるわけではありません。「信義則に反し」など他の要件も満たして、「消費者の権利を一方的に害する」と判断された場合には無効になるということです。
3. 事業者の損害賠償責任を免除する条項は無効
抽象的な第10条のほかに、個別具体的な不当条項も定められています。第8条は、「事業者の損害賠償責任を免除する条項」です。条文は細かく分かれていますが、まとめてざっくり言うと、「事業者の債務不履行や不法行為によって消費者に損害を与えても、事業者は一切責任を負わない」「消費者の損害の原因が事業者の故意または重大な過失であっても、損害賠償額は○円を限度とする」といった内容が不当とされます。
例えば、「不良品でも修理も交換もしない」という条項は、無効になる可能性が高そうです。「修理はしないが代替品を送る」であれば無効にはなりません。「不良品の返品・交換対応の申し出は、商品受領後○日以内とする」という条項は第8条には該当しませんが、申し出可能な期間があまりに短い場合は、第10条で「消費者の権利を不当に制限する」と判断される可能性があります。(注:ここで言う返品や交換は、あくまで事業者側に原因がある場合の話です。消費者都合の返品は、法的には全く別の扱いですので、混同しないようにしてください。)
他にも、冠婚葬祭のような大事な日に使うものが発注ミスで間に合わず、消費者が代替品を手配しなければならなかった、欠陥商品で消費者が怪我をした、そういったケースで、「当社は損害賠償の責任を負いません」と規約に書いておけば逃げられるかというと、そうはいかないということです。「賠償額は商品代金を限度とします」は、事業者のミスが軽微な場合に限定されていれば良いですが、重大な過失にも適用されるように読めると無効とされてしまいます。「賠償の責めを負うかどうかを当社が判断します」も認められません。
4. 消費者の解除権を放棄させる条項は無効
2016年改正で第8条の2が追加され、「契約成立後のキャンセルは一切受け付けない」といった条項は無効とされました。事業者にミスがあったり商品に問題があったりすれば消費者に契約解除の権利が発生しますが、それを放棄させるのは不当という趣旨で、あくまで契約成立後の話です。
2018年改正では、上記の場合に消費者に解除権があるかどうかを事業者が判断する、という条項も無効とされました。
もう1つ、2018年改正で「消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由に事業者に解除権を付与する条項」(第8条の3)が追加されましたが、Eコマースでは見たことがなく、あまり気にしなくて良いように思います。
5. 高額な違約金を定める条項は無効
第9条です。「契約解除に伴い、事業者に生ずる平均的な損害の額を超えるような違約金を消費者に課す条項は、その超えた分が無効」という規定です。結婚式場のキャンセル料などが念頭にあり、Eコマースでは想定しにくいかも知れません。
消費者が、キャンセル料が高過ぎるとクレームしたい場合、この規定では、「平均的な損害の額を超える」ことを消費者側が立証しなくてはならず、実際には使えないという声が以前からありました。消費者契約法の見直しのたびにテーマとされてきましたが、まだ決着はついていません。現在、消費者庁で検討中の次回改正では、何らかの方向性が出てくるようです。
グローバルなITサービスや国内大手プラットフォームの利用規約を念頭に、不当条項規制を厳しくすべきとの主張は根強く、見直しの議論は今後も続くと思われます。
また、消費者契約法では、適格消費者団体による差止請求が認められています。規約に書かれていることと実際の運用は同じではないと思いますが、消費者トラブルが発生しているか否かに関わりなく、趣旨が不明確で消費者に不利との誤解を生じさせる条項があると、適格消費者団体から改善の申し入れが寄せられるかも知れません。
消費者契約法についても、改正動向や差止請求の状況に注意し、自社の利用規約やその他契約条件に不当とみなされる可能性のある部分が無いか、点検をお勧めいたします。
消費者契約法の条文や逐条解説は、消費者庁の解説ページに掲載されています。
→各法律の条文や解説などは、以下のページに掲載されています。
定型約款と利用規約の関係については、経済産業省の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(I-2)でも解説されていますので、そちらもご参照ください。